男性産休の「期間」迷っていませんか?今知るべき取得ルール
男性も産休・育休を取得できる時代になりましたが、「実際どのくらいの期間取れるの?」「分割取得や申請方法は?」と迷う方は少なくありません。本記事では、最新法改正による男性産休の取得ルールや具体的な期間、実際の取得状況、職場・家庭での注意点まで、要点と実例を交えて詳しく解説します。
>妊活・妊娠・育児に関する悩みを相談できるカウンセラーはこちら男性産休の期間はどれくらい?制度の基本ルールと最新法改正ポイント
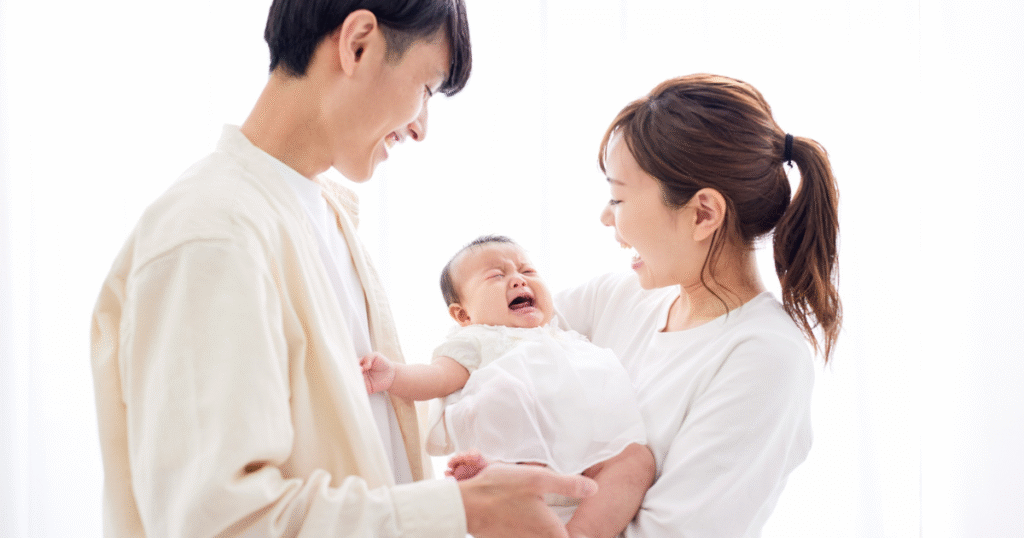
男性が取得できる産休や育休制度は、法改正を経て選択肢が広がっています。従来、育児休業は女性中心のイメージがありましたが、現在は男性も対象となり、最長2年や分割取得など柔軟な利用が可能です。また、2022年の法改正で「産後パパ育休」も新設され、出産直後のサポートがしやすくなりました。これにより、男性の育児参加がより現実的かつ積極的に進められる社会環境が整いつつあります。ここでは主要な制度の期間や取得条件、手続きのポイントを整理します。
男性産休は最長2年取得可能
男性が取得できる育児休業の期間は、原則として子どもが1歳になるまでですが、保育園に入れないなど一定の事情があれば最長2歳まで延長できます。育児と仕事の両立を希望する家庭は増えており、実際に延長を選ぶケースも見られます。職場復帰のタイミングや保育環境の状況にあわせて柔軟に期間を設定できる点は、多様な家庭事情に配慮した制度設計といえるでしょう。
産後パパ育休は4週間まで
2022年の法改正で創設された「産後パパ育休」は、出生後8週間以内に最大4週間まで取得できます。この期間は、通常の育児休業とは別枠として設けられているため、出産直後のサポートに特化した短期休暇です。パートナーの心身の負担が大きい出産後、積極的に育児や家事に参加しやすい環境を整えるために役立つ制度です。
2022年法改正で分割取得可
2022年の改正育児・介護休業法により、男性の育児休業は分割して2回まで取得できるようになりました。たとえば、産後すぐとパートナーの職場復帰タイミングなど、家庭の都合に応じて柔軟に取得時期を調整できます。分割取得が可能になったことで、男性もより実態に即した育児参加がしやすくなっています。
事前申請で取得がスムーズに
育児休業や産後パパ育休を希望する場合、原則として申請は事前に行う必要があります。産後パパ育休は原則2週間前まで、通常の育児休業も1か月前までの申請が求められます。職場との調整や業務引き継ぎを円滑に進めるためにも、早めの相談と申請が取得の鍵となります。取得希望がある場合は、早めに会社へ意向を伝えましょう。
取得条件はパートナー次第
男性産休や育休の取得には、配偶者が出産することが前提です。また、産後パパ育休も同様に、出生後8週間以内という限られた期間のみ取得できます。パートナーの体調や家庭の事情により、取得時期や期間を検討する必要があります。職場や家庭の状況によって最適な取得方法は異なるため、パートナーとよく相談しながら進めることが重要です。
育休と産後パパ育休の違いと取得できる期間の具体例
男性の「産休」は法律上「育児休業」と「産後パパ育休(出生時育児休業)」の2種類に分かれます。それぞれ取得できる期間やタイミング、分割取得の条件が異なるため、混同しやすい点が特徴です。ここでは育児休業と産後パパ育休の違い、および具体的な期間や取得例について解説します。最新の法制度に基づき、イメージしやすい実例とともにポイントをまとめます。
育休は子が1歳になるまで
育児休業は、原則として子どもが1歳の誕生日を迎える前日まで取得できます。保育園に入れないなど一定の事情があれば、最長2歳まで延長することも可能です。たとえば、2024年4月1日生まれの子どもなら、2025年3月31日まで育休を取得できます。実際に取得する期間は、家庭や職場の状況により調整でき、復職時期との兼ね合いで数か月単位の取得も選択できます。男性もこの制度を利用でき、職場の制度を確認しながら申請することが重要です。
産後パパ育休は8週以内
産後パパ育休(出生時育児休業)は、子どもの出生後8週間以内に取得できる制度です。取得可能期間は最長4週間で、この期間中に分割して取得することも認められています。たとえば、子どもの出生日が2024年5月1日なら、2024年6月26日までの間に4週間を分けて取得できます。出産直後のサポートや、母親の心身の負担軽減を目的に活用されるケースが多いのが特徴です。
育休は最長2回に分割可
育児休業は、法律により最長2回まで分割して取得できます。たとえば、子どもが生まれてすぐに1回目の育休を取得し、いったん職場復帰。その後、もう一度2回目の育休を申請するといった使い方が可能です。この分割制度により、保育園の入園時期や家庭の状況に合わせて無理なく働き方を調整できる点がメリットです。
パパ育休は育休とは別枠
産後パパ育休(出生時育児休業)は、育児休業とは別枠で取得できます。つまり、出産後8週間以内に「産後パパ育休」を取得した上で、その後に「育児休業」を申請することが可能です。両制度を組み合わせることで、出産直後から子どもが1歳(一定条件で2歳)になるまで、長期間にわたり家族をサポートできます。
両方の制度を活用することで、男性もより主体的に育児に関わることができ、家族のライフスタイルや状況に応じて柔軟な働き方が可能となります。
男性産休の平均取得期間と現場の実態
男性が取得する産休の期間は、表向きには制度として認められているものの、実際の取得状況や職場の受け入れ体制には大きな差があります。平均的な取得期間や取得率、企業ごとの推奨度など、働くママが気になる「現場のリアル」を多角的に整理します。パートナーの産休取得を検討中の方や、今後の取得をサポートしたい方に向けて、具体的なポイントを解説します。
平均取得期間は約2週間
厚生労働省の調査などによると、男性が実際に取得している産休や育休の期間は平均して約2週間程度が多い傾向にあります。これは法律上取得できる最大期間と比べて非常に短く、制度を活用しきれていない現状を示しています。家庭の事情や職場の理解度により期間は前後しますが、取得経験者の多くが「短期間での復帰」を選択していることが実態です。復職後のサポート体制や育児の負担分担を考えると、もう少し長期の取得が望ましいと感じる方も多いのではないでしょうか。
実際の取得率は低い
男性の産休や育休取得率は、近年ゆるやかに上昇しているものの、依然として全体から見ると低水準にとどまっています。取得率が伸びない理由としては、職場の風土や業務の引き継ぎ体制が整っていないこと、上司や同僚の理解不足などが挙げられます。特に企業規模や業種によっても取得のしやすさに違いがあり、十分な環境が整っていない場合は「取りたくても取れない」状況となりがちです。
職場の理解が必要不可欠
男性が産休を取得しやすい環境を作るには、職場全体の理解と協力が不可欠です。制度自体があっても、業務の調整や周囲のサポート体制がなければ、取得をためらう男性も多いのが現状です。実際、職場の上司や同僚からの肯定的な声かけや、業務分担の工夫があることで取得に踏み切れたという声も聞かれます。働くママの立場からも、パートナーの産休取得には周囲の協力が大きな後押しになるでしょう。
短期取得が多い現状
男性の産休取得が短期間にとどまる背景には、職場復帰へのプレッシャーや「長く休むと職場に迷惑がかかる」という心理的負担があります。そのため、実際には1〜2週間ほどで復帰するケースが目立ちます。育児や家事の負担をパートナーと分担するうえでは、もう少し柔軟かつ長期的な休暇取得が求められますが、現状は短期取得にとどまる傾向が根強いです。
企業によって取得推奨度が異なる
男性産休の取得推奨度は企業ごとに大きく異なります。大手企業や人材定着を重視する企業では、積極的に取得を促進する取り組みが進んでいますが、中小企業や一部の業界ではまだまだ浸透していません。企業ごとの方針やサポート体制が、取得しやすさに直接影響するため、事前に職場の状況をしっかり確認することが大切です。パートナーと話し合う際にも、企業文化や実際のサポート内容を調べておくと安心です。
男性が産休・育休期間を決める際によくある悩みと注意点
男性が産休や育休の期間を設定する際、多くの家庭で複数の悩みや不安が生じます。期間の目安が分かりづらいことや、育休中の収入減少、家族や職場との調整、法律と実際の運用にギャップを感じる点などが代表的です。また、企業や職種によっては制度の活用が進んでいない場合もあり、復職時の不安も残ります。男性が産休・育休期間を決める際は、さまざまな視点からの検討と周囲との十分なコミュニケーションが不可欠です。ここでは、男性が産休・育休期間を決める際に直面しやすい悩みと、その注意点を整理します。
取得期間の見極めが難しい
男性が産休・育休の期間を決める際、どのくらい取得すればよいか迷うことが多いです。法律では育児休業の上限は決まっているものの、実際にどの程度休むべきかは家庭の状況や職場の体制によって異なります。パートナーの体調や育児の負担、職場の理解度なども判断材料となるため、最適な取得期間は各家庭で異なります。
身近な経験者や専門家の意見を参考にしながら、家族で十分に話し合いましょう。
職場復帰のタイミングが心配
育休取得後、職場復帰のタイミングに不安を感じる男性も少なくありません。復帰時期が遅くなると、仕事の流れや人間関係に遅れを取るのではという懸念が生まれます。特に、業務の属人化が強い職場や男性育休が少ない環境では、復職後の立ち位置や評価を気にする声が多く聞かれます。
収入減少の不安がある
育休期間中は、給与が減る、もしくは支給されないケースがあります。育児休業給付金など公的支援はあるものの、手取りは通常の給与より低くなる場合がほとんどです。家計への影響を心配する男性も多いため、制度上の給付金や支給条件を事前に確認し、備えを行うことが重要です。
家族の理解が必要不可欠
男性が産休や育休を取る際、家族の理解と協力は欠かせません。パートナーや祖父母など、それぞれの立場や事情によって意見が分かれることもあります。家事や育児の分担について具体的に話し合い、役割を明確にすることで、家族全体の負担軽減やスムーズな育休取得につながります。
法律と実態のギャップ
法律上、男性も産休・育休を取得する権利がありますが、実際の職場では取得しづらい雰囲気や制度運用の壁が存在します。業務の引き継ぎ体制が不十分、前例がない、上司や同僚の理解が得られにくいなどの理由で、制度と現実のギャップを感じるケースが多くなっています。
こうした状況では、個人だけで悩まず、外部の専門家やカウンセラーの助言を活用するのも一つの方法でしょう。
NOALONでは、臨床心理士などのカウンセラーに オンライン で悩みを相談することができます。
男性産休中の給付金や社会保険の免除制度
男性が産休や育休を取得した場合、経済的な不安を軽減するための支援制度が複数用意されています。主なものとして、育児休業給付金の支給や社会保険料の免除、年金保険料の特例措置があります。これらの制度を知ることで、休業中の生活設計や働き方の選択肢が広がります。以下で、それぞれのポイントや手続きについて解説します。
育休給付金は賃金の67%
育児休業給付金は、男性が育児休業を取得した場合に雇用保険から支給されます。休業開始から180日間は、休業前の賃金の67%が支給される仕組みです。これは、生活費の大部分をカバーできる水準となっています。181日目以降は50%に減額されますが、一定の収入を確保しながら子育てに専念できる点が大きなメリットです。給付金の金額は、休業開始前6カ月間の平均賃金から計算されます。育児と仕事の両立を目指す際、経済的不安を和らげる重要な支援となっています。
社会保険料は免除される
育児休業期間中は、健康保険や厚生年金などの社会保険料が原則として免除されます。保険料の負担がなくなるため、手取り額が減少しても生活への影響を抑えられるのが特徴です。免除期間中も、将来の年金受給資格や健康保険の給付資格には影響しません。企業の給与明細などで保険料が引かれていないことを確認することも大切です。この制度により、休業中の家計負担を大きく軽減できます。
給付金は2ヶ月ごと支給
育児休業給付金の支給は、2ヶ月ごとにまとめて行われます。申請後、雇用保険から指定口座へ直接振り込まれるため、まとまった金額を受け取れる点が特徴です。受給には、2ヶ月ごとに「育児休業給付金支給申請書」を提出する必要があります。必要書類や手続きのタイミングを事前に確認しておくことで、スムーズに給付金を受け取ることができます。休業期間の生活設計を立てる際は、この支給サイクルも意識しましょう。
年金の支払いも免除可能
育児休業を取ると、厚生年金保険料の支払いも免除されます。免除期間中も将来の年金受給額に影響はなく、保険料を納めたものとして扱われます。これにより、休業中の負担を感じることなく安心して育児に専念できます。免除申請は、通常会社が手続きを行いますが、不明な点があれば人事労務担当に確認するとよいでしょう。生活費や将来設計においても、この免除制度が大きな支えとなります。
申請手続きは事業主が代行
育児休業給付金や社会保険料免除などの申請手続きは、原則として勤務先の事業主が代行します。従業員本人が行う手続きは少なく、必要書類の提出や記入だけで済むケースがほとんどです。安心して制度を利用するためにも、休業前に会社の担当部署と必要な手続きやスケジュールを確認しておきましょう。制度の活用にあたり、わからない点や不安があれば早めに相談することがスムーズな取得につながります。
パパ・ママ育休プラスや分割取得など柔軟な取得パターン
男性産休や育児休業の取得方法は、近年、家族の状況や職場復帰のタイミングに合わせて柔軟に選べるようになっています。パパ・ママ育休プラスや分割取得、夫婦で交代しての取得など、多様なパターンが実現可能です。制度を上手に活用すれば、育児と仕事の両立がしやすくなり、家族の負担も分散されます。ここでは、主な柔軟取得のパターンと条件について具体的に解説します。
パパ・ママ育休で期間延長
パパ・ママ育休プラスは、父母がともに育児休業を取得することで、原則1歳までの育休期間を最長1歳2か月まで延長できる制度です。例えば、母親が産後休業後に育休を取得し、その後父親が一定期間内に育休を取ると、両者の合計で育休期間が長くなる仕組みです。この制度を活用すれば、より長い期間家族で育児に専念できるため、復職前の準備や産後の心身の回復にも役立ちます。実際に、夫婦で交互に取得するケースも増えており、仕事と育児の両立を支える上で重要な選択肢になっています。
分割取得で職場復帰が柔軟
2022年の法改正により、育児休業は最大2回まで分割取得が可能となりました。これにより、たとえば子どもの成長や保育園入園のタイミングに合わせて、必要な時期ごとに休業を取得できます。職場復帰までの準備期間を調整しやすくなり、復帰後の適応負担も軽減できます。また、分割取得により一時的な人手不足リスクも分散されるため、企業側にもメリットがあります。産休・育休中の女性にとっても、パートナーがこうした柔軟な取得を選ぶことで、家族全体のサポート体制が強化されるでしょう。
夫婦で交代取得が可能
育児休業は、夫婦で交代しながら取得することも認められています。例えば、母親が産後すぐに育休を取得し、その後父親がバトンタッチして育休を取るといった形です。これにより、一人が長期間仕事を離れる負担を分散でき、キャリアへの影響も最小限に抑えられます。交代取得により、子どもと過ごす時間を夫婦それぞれがしっかり確保できるのも大きな利点です。職場復帰の時期や働き方の調整を夫婦で話し合いながら決めるケースが増えています。
育休期間の延長条件あり
育児休業の延長には一定の条件があります。たとえば、子どもが1歳を迎える時点で保育園に入れないなどの事情がある場合、1歳6か月または最長2歳まで延長可能です。ただし、延長には自治体や企業への申請手続きが必要で、期間や取得理由も厳格に審査される点に注意が必要です。手続きや条件の詳細は、職場の人事部や自治体窓口で早めに確認しておくと安心です。延長を希望する場合は、必要書類や申請時期を事前に把握し、計画的に準備しましょう。
柔軟な取得で家族支援強化
柔軟な育休取得パターンは、家族の生活や一人ひとりの心身の健康を守るために有効です。特に、パートナーの取得タイミングや期間を調整することで、子育ての負担を分担しやすくなります。実際に、育児休業を活用した家庭では、育児ストレスの軽減や家族関係の円滑化につながったという声も多く聞かれます。柔軟な制度を積極的に活用し、家族全体のサポート体制を整えることが、安心して仕事と育児を両立する第一歩です。
男性の産休・育休取得をめぐる職場と家庭の心理的不安への対策
男性が産休や育休を取得する際、制度は整っていても「実際に活用するにはさまざまな心理的ハードル」が存在します。職場では、「業務に穴を開けてしまうのでは」という不安や、周囲の理解不足が壁となりやすい状況があります。一方、家庭ではパートナーとの役割分担や育児への自信のなさがストレスの要因となることも少なくありません。こうした状況を乗り越えるためには、職場と家庭の両方での理解促進と、適切なメンタルケア体制の整備が不可欠です。具体的な対策について、以下で詳しく解説します。
職場の理解促進が重要
制度として男性の産休や育休が整備されていても、実際の取得率を高めるには職場風土の改革が不可欠です。管理職や同僚が制度の意義を深く理解し、取得を積極的に後押しする体制を築くことが、取得希望者の心理的負担を大きく減らします。例えば、取得経験者の体験談を社内で共有したり、制度利用を評価項目に加えたりすることが有効です。職場全体で「支え合う」姿勢が根付けば、男性の産休・育休取得はより現実的な選択肢となります。
家族間のコミュニケーション強化
産休・育休期間中は、家族間で率直に気持ちや希望を伝え合うことが何より大切です。男性が育児や家事にどう関わるか、パートナーと事前に役割分担を話し合って明確化することでトラブルを未然に防げます。また、日々の負担や不安を共有し合うことで、孤立感や自信喪失を和らげる効果があります。育児や家事の知識不足は、学習や外部サポートの活用で補うことが可能です。
NOALONのカウンセリング活用
産前産後や育児の悩みに特化したオンラインカウンセリングサービスを利用することで、男性自身や家族の心理的負担を効果的に軽減できます。国家資格保有者との相談が24時間365日予約可能なため、忙しい育児や仕事の合間でも利用しやすいのが特徴です。顔出し不要・会員登録不要という匿名性の高さは、初めて利用する方の不安も和らげます。メンタルケアの選択肢が増えることにより、家庭全体の安心感や満足度が向上します。また、急な不安や悩みにもすぐ相談できる窓口があれば、問題の深刻化を防げます。メンタルケアは一時的なものではなく、復職や育児継続の過程でも継続的に受けられる環境づくりが重要です。
男性産休の期間・取得ルールまとめ
男性産休の取得期間やルールは、法改正により柔軟性が増し、最大2年の育休や産後パパ育休の分割取得など、多様な働き方・家族形態に対応できるようになっています。しかし現場では、取得率や期間にはばらつきがあり、職場や家庭の理解、実際の取得タイミングなど悩みも多いのが実情です。育休中の給付金や社会保険の免除、分割取得など制度を正しく理解し、自分と家族に合った選択をすることが大切です。もし「育児や産後の不安」「職場復帰や家族関係の悩み」「制度を活用する際の心理的なハードル」などで迷いや不安がある場合は、専門家によるカウンセリングを活用するのも一つの方法です。
NOALON -ノアロン- では、国家資格保有カウンセラーによる産前産後・育児特化のオンラインカウンセリングを24時間365日ご予約いただけます。育児の悩みを一緒に解決しましょう。
>妊活・妊娠・育児に関する悩みを相談できるカウンセラーはこちら

